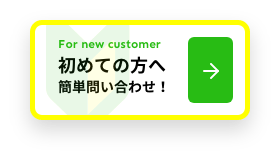撮影ディレクションは「言葉より、資料」! 参考事例の作り方と渡し方
完成した家の魅力をしっかり写真で伝えたい。
そんな想いで撮影を依頼しても、仕上がった写真を見て「思っていた雰囲気と違う…」と感じたことはありませんか?
その原因の多くは、ディレクションの“伝え方”にズレがあったこと。
口頭で「ナチュラルであたたかい雰囲気で」「素材感が伝わるように」と説明しても、言葉の解釈は人によって微妙に異なります。
だからこそ、撮影の現場では「言葉より、資料」が断然効果的。
今回は、撮影の意図を的確に伝えるための“参考資料の作り方”と“渡し方のコツ”をご紹介します。
■ 撮影ディレクションでよくあるすれ違い
たとえば「自然光を活かした写真で」と伝えても…
Aカメラマン:「明るさ重視で窓越しの白飛びもOK」
Bカメラマン:「やわらかい陰影を活かした夕方の光」
どちらも間違いではありませんが、依頼者の意図とズレることがあるのです。
こうした認識のギャップをなくすには、「この写真のように」と目で共有できる参考資料が何より有効です。
■ “伝わる資料”のつくり方3ステップ
① 参考になる他社事例や過去の自社投稿をピックアップ
「この写真のトーンが理想」「この構図が使いやすい」など、完成イメージに近い例を具体的に並べて見せると、撮影イメージが共有しやすくなります。
② 「どこを、何のために撮るか」を整理して記載
場所だけでなく、「リビングの奥行き感」「造作棚のディテール」など、意図がわかる一言メモをつけましょう。
→ 撮る側も「この視点が大事なんだ」と理解しやすくなります。
③ 用途に合わせて見せ方も指定しておく
SNS用 → 正方形にトリミングしても映える構図
ホームページ用 → 横長構図+抜け感重視
印刷用 → 高解像度/自然光多め
活用目的が分かると、撮影者も“仕上がりのゴール”を想像しやすくなります。
■ 渡し方のコツは「撮影前+当日補足」
資料は事前にPDFや共有リンクでカメラマンに送付し、当日は印刷して持参するのがおすすめです。
撮影当日の立ち会いができる時には…
現場の光の入り方に合わせて一部カットの調整
撮り漏れ防止のためのチェックリスト活用
撮影後、「このカットでよさそうですね」と軽く確認
こうすることで、広報と撮影チームが“同じ完成イメージ”を共有しながら進められます。
■ おわりに
写真で伝えたいのは、“空間”だけでなく“想い”です。
その想いを伝えるには、言葉よりも視覚的に共有できる資料が最も効果的。
特に、撮影を外注している場合やカメラマンが毎回変わる場合は、資料の有無が仕上がりに大きく影響します。
「撮ってほしい」ではなく、「こう見せたい」を伝える。
その一歩として、参考資料づくりをぜひルーティンに取り入れてみてください。